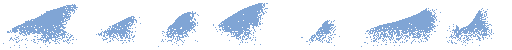
諏訪大社上社前宮 すわたいしゃかみしゃまえみや 長野県茅野市宮川2030 Tel 0266-72-1606 1.jpg)
尖石縄文考古館 とがりいしじょうもんこうこかん 長野県茅野市豊平4734ー132 Tel 0266-76-2270 
蓼科高原三井の森
乙事諏訪神社 おっことすわじんじゃ 長野県諏訪郡富士見町大字乙事5410 Tel 0266-62-9342 富士見町役場産業課 1.jpg)
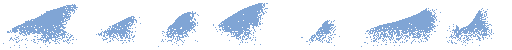 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
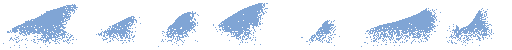
諏訪大社上社前宮 すわたいしゃかみしゃまえみや 長野県茅野市宮川2030 Tel 0266-72-1606 1.jpg)
尖石縄文考古館 とがりいしじょうもんこうこかん 長野県茅野市豊平4734ー132 Tel 0266-76-2270 
蓼科高原三井の森
乙事諏訪神社 おっことすわじんじゃ 長野県諏訪郡富士見町大字乙事5410 Tel 0266-62-9342 富士見町役場産業課 1.jpg)
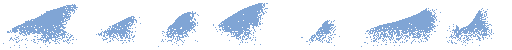 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||